Q.女性や子供でも扱えますか?
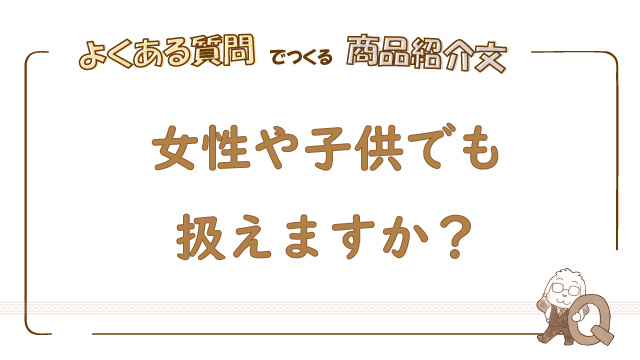
商品紹介文を書く時に使える「よくある質問」。今日の“質問”はこちら!
![]() 『女性や子供でも扱えますか?』
『女性や子供でも扱えますか?』
近年、女性のファンが多くなっているDIYの世界。
DIYをする女性の動画がたくさん配信されるなど、女性や若い人にもとても身近なものになってきています。
元々は“技術を持っている、限られた男性”がメインだったDIYの世界。
それを女性や子供にも広げたことでDIYの世界は客層を大きく拡げることに成功しました。
あなたの商品・サービスでも、「元は女性向けの商品だったけれど、男性にも対象を広げた」、「最初は大人のお客さんだけを想定していたけど、お子さんが来ても良いようなサービスに改良した」といったように、客層を拡げた商品・サービスはないでしょうか?
もしあるのなら、ぜひこの質問で商品アピールをしていきましょう!
この電動ドリルは女性でも扱えますか?

女性のご愛用者様もたくさんいらっしゃいます。その“理由”は…
はい、女性のご愛用者様もたくさんいらっしゃいます。
女性人気が高い理由は3つ。
1)270gと軽く、コードレスタイプなので、女性でも取り回しがラクラク。
2)電動工具は怖い・危険と思っている女性ユーザーのため、「速度切り替えレバー」をつけました。
3)デザインは女性スタッフが担当。ピンクや蛍光色ではなく、落ち着いたモノトーン。
このように書かれていたら、「女性向けの製品なんだな」、「女性のワタシに合っているんだな」ということが伝わりますね。
・・・
「我が家でも使えるのかな?」と心配になるようなモノも、このQ&Aを書いておくことで安心して買っていただくことができます。
たとえば…
ランニングマシンをマンションで使いたいと思っています。下の階に音が響くことはありますか?

「下の階に響きにくい」設計で、マンションでも安心です。
室内や夜間に使うことを想定し、スプリングを強化したモデルですので、使用時の音が響きにくい構造になっています。
もしご心配でしたらオプションの「静音マット」を併用下さい。より静かにご使用いただくことができます。
※ 実際に使用している様子の動画がございますので、こちらも参考になさって下さい
・・・
使用するのに何かしらの“条件”がある商品の場合、それを購入前に知っておいていただかないと、“返品”や“クレーム”につながってしまうということもあるでしょう。
しかし、お客さんは意外とそういう説明を読まないことも少なくありません(^_^;)
「そんな条件があるとは知らなかった」と返品や解約をされてしまうのは、売上的にも精神的にもダメージ…。
そこで、説明文をあえて「よくある質問」のカタチにして、ちゃんとわかっていただくようにしていきましょう。
この動画配信サービスは、1つの契約で何人が同時に視聴することができますか?

1契約につき、2台まで同時にご試聴いただけます
1契約で同時に視聴できる(パソコン・スマホ)のは「2台」までです。
また同じ作品を同時に2台以上で見ることはできません(※別作品を同時に見るのは可能)
サービスの説明文にも書いておき、さらに「よくある質問」でも書いておく…“条件”をちゃんと理解してから購入・契約していただけるようにするためには、そのような工夫も大切です。
![]() 『女性や子供でも扱うことができますか?』
『女性や子供でも扱うことができますか?』
![]() 女性のご愛用者様もたくさんいらっしゃいます。その“理由”は…
女性のご愛用者様もたくさんいらっしゃいます。その“理由”は…
![]() こんな工夫がされているので、安心です。
こんな工夫がされているので、安心です。
![]() いくつまで同時に使えます / 何名様までご利用いただけます
いくつまで同時に使えます / 何名様までご利用いただけます
新たな客層に向けて改良した商品・サービスなら、ちゃんと「その人たちに向けた商品」であることをアピールしていきましょう。
使用するのに“条件”がある場合も、明示しておくのが大切です
--- 「ことのは塾」 山梨 栄司

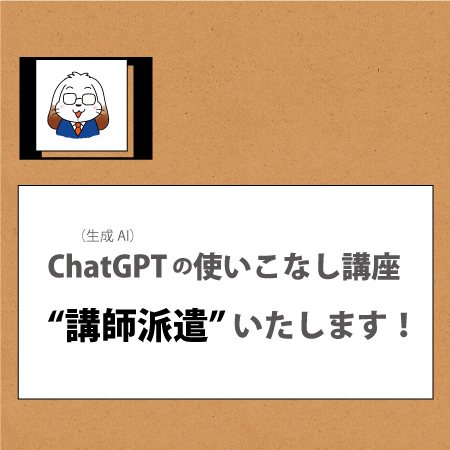
今、話題のChatGPT(「生成AI」)。
・ 展示会の「チラシ」の内容を考えてくれたり、
・ 会議用の資料やタイムスケジュールをうまく作ってくれたり、
・ 社内にある売上データや「お客さまアンケート」などのデータを分析してくれたり
と、『業務の効率化』や『業務のレベルアップ』に非常に役立っています。
・・・・
ソフトバンクの孫さんなど大企業のトップも活用している、この新技術。
しかし、もっと大きなインパクトを享受できるのは、実は「中小企業」や「小さなお店」。
一人のスタッフが、いくつもの仕事を柔軟にこなす必要がある会社やお店であればあるほど、"様々な仕事のアシストができる"ChatGPTの恩恵は大きくなります。
・・・・
しかし…
私たちにご相談いただく企業やお店から伺ったところ、
☆ ChatGPTを社内に導入したいが、何から始めたら良いのかわからない…
☆ 我が社ではどんなことに使えるのか? 今ひとつつかみきれない…
☆ 「新しいことを覚えたくない」、「自分の仕事を奪われるのでは?!」と社員が前向きになってくれない……
といった“声”があるのも事実です。
・・・・
そこで私たち「ことのは塾」は、『日本一ハードルの低い ChatGPT講座』と題して、ChatGPT初心者にもとっつきやすい研修プログラムを提供させていただいております。
興味を持っていただけましたら、ぜひこちらのページもご覧になってみて下さい!



