Q.「良い○○」を選ぶには、どこを見ればいいですか?
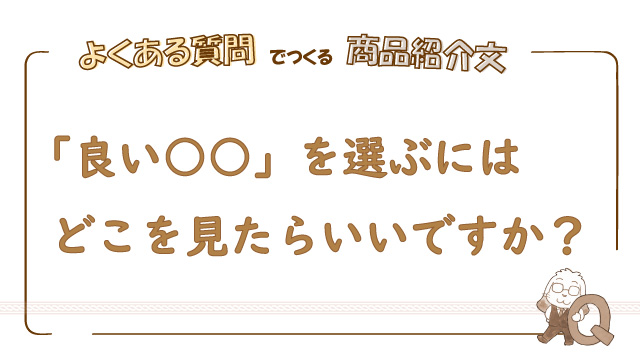
![]() 「良い○○」を選ぶには、どこを見ればいいですか?』
「良い○○」を選ぶには、どこを見ればいいですか?』
あなたの商品・サービスでこの“質問”に答えてみましょう!
ここで聞かれているのは「目利きのポイント」。
たとえば、おいしいりんごを見極める“目利きポイント”は「色・おしり・軸を見ること」だといいます。

・全体的に赤く、色つやの良いりんごは甘みが強く、味が濃いです
・おしりの部分が光っているように見えるりんごは蜜が入っていますよ
・軸の部分は栄養を行き渡らせるパイプの役目。だから、ここが太いりんごは甘みが詰まっています!
この情報を知っていたら、おいしいりんごを選ぶことができますね。
そんな“目利き”のポイントを、プロであるあなたはよく知っているのではないでしょうか?
・・・
あなたの扱っている商品がサービスであっても同じです。
「良い“家事代行サービス”を選ぶには、どこを見たら良いですか?」
とお客さんが聞いてきたと考えてみて下さい。
・ 家事代行サービス認証を取得している企業が安心です
・ 料金設定がシンプルなところは、後から「オプション料金がこんなにかかるの?!」というトラブルがありません
・ まずはメールや電話で質問してみましょう。回答が丁寧な会社は安心です。逆に訪問日をぐいぐい決めさせてくる会社は要注意です
といったように、サービスであっても“目利きのポイント”があるでしょう。
・・・
こうして“目利きポイント”を教えてあげることで、お客さんが商品を見るポイントがハッキリします。
「りんごは“おしり”を見る」とわかれば、お客さんはりんごの“おしり”を見るようになります。
あなたのりんごの“おしり”が光っていれば、「あ、これは良いりんごなんだな」とわかってもらうことができますね。
商品紹介文を書こうとする時…自分に「Q.「良い○○」を選ぶには、どこを見たらいいですか?」という質問をすることで、「この商品はココを見てもらいたい!」とあなたがそう思っているトコロ、自慢のポイントにお客さんの視点を誘導することができるわけです。
・・・
この質問への回答は、あなたが自社商品のアピールポイントだと思っている点を挙げて下さい。
「ココを見てほしい!」
「この部分は他店さんより優れているから、ぜひ注目してもらいたい」
「ここにチカラを入れているから、ぜひ知ってほしい」
そんな風にあなたが思っている点、それこそがここで挙げるべきポイントです!
挙げるポイントの「数」に決まりはありませんが、3つくらいのポイントを挙げると読みやすさと説得力のバランスが取れやすいでしょう。
あなたの商品・サービスを選ぶ時…お客さんはどこを見たらいいでしょうか? ぜひ教えて下さい!
![]() 『「良い○○」を選ぶには、どこを見ればいいですか?』
『「良い○○」を選ぶには、どこを見ればいいですか?』
![]() “目利きのポイント”や“お客様に注目してほしい点”、“あなたの商品の自慢できるところ”を描きましょう!
“目利きのポイント”や“お客様に注目してほしい点”、“あなたの商品の自慢できるところ”を描きましょう!
--- 「ことのは塾」 山梨 栄司

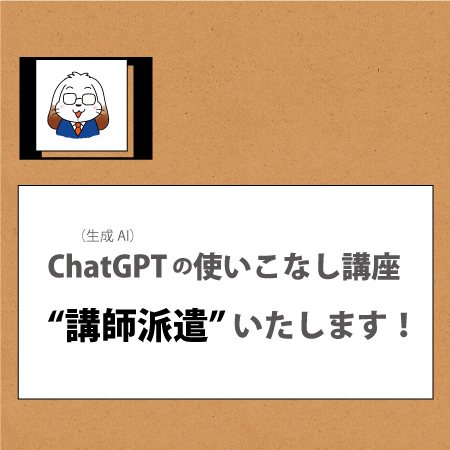
今、話題のChatGPT(「生成AI」)。
・ 展示会の「チラシ」の内容を考えてくれたり、
・ 会議用の資料やタイムスケジュールをうまく作ってくれたり、
・ 社内にある売上データや「お客さまアンケート」などのデータを分析してくれたり
と、『業務の効率化』や『業務のレベルアップ』に非常に役立っています。
・・・・
ソフトバンクの孫さんなど大企業のトップも活用している、この新技術。
しかし、もっと大きなインパクトを享受できるのは、実は「中小企業」や「小さなお店」。
一人のスタッフが、いくつもの仕事を柔軟にこなす必要がある会社やお店であればあるほど、"様々な仕事のアシストができる"ChatGPTの恩恵は大きくなります。
・・・・
しかし…
私たちにご相談いただく企業やお店から伺ったところ、
☆ ChatGPTを社内に導入したいが、何から始めたら良いのかわからない…
☆ 我が社ではどんなことに使えるのか? 今ひとつつかみきれない…
☆ 「新しいことを覚えたくない」、「自分の仕事を奪われるのでは?!」と社員が前向きになってくれない……
といった“声”があるのも事実です。
・・・・
そこで私たち「ことのは塾」は、『日本一ハードルの低い ChatGPT講座』と題して、ChatGPT初心者にもとっつきやすい研修プログラムを提供させていただいております。
興味を持っていただけましたら、ぜひこちらのページもご覧になってみて下さい!



